RMAAテストについて
機材の比較や情報交換によく用いられる RMAA でテスト.
テストトーンの送り出し/受け側の機材にデジタルミキサー Tascam DM-24を使用.
→ RMAA: 録音/再生 (16bit/44.1kHz, 24bit/96kHz, 電池駆動)
数値で見た結果の概要は
|
まず最初に周波数特性についてふれると,24bit/96kHz録音時に
40kHzまでほとんどフラット(-6dB未満の落ち込み)なのに驚く.
一方,44.1kHz時には20kHzでスパっと落ちている.まともすぎる.
さらにS/Nが凄くいい.信じられないくらい.

|
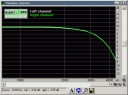
|
| 44.1kHz録音時の高音域 | 96kHz録音時の高音域 |
それなのに・・・歪み特性はあまりよくない.
いや,まあまあ普通なんだけど,これだけのS/Nと周波数特性を示す
近年のデジタル物としては物足りない.
実は「一般的なデジタルレコーダと挙動や質感が違うなあ」と聴感で感じていた.
この歪みの数値をきっかけにいろいろと掘り返すことになった.
| 結論から言うと,RMAAのテスト結果の0.3〜0.4前後のTHD/IMD値は ゲインLのみにみられる歪みで,入力アンプが若干オーバードライブしている感じ. 少し入力レベルを落とせばH4での正常値 (0.1前後) に落ち着く. |
録音時のわずかな歪みについて
Zoom H4で録音するとき,3つの歪みがあることがわかった.
| 1.大きな音を入力すると高音域が失われる歪み 入力部のエンファシス/デエンファシス回路によるもの 2.ゲインLで大きな音を入力すると高調波が発生する歪み 入力アンプが軽くオーバードライブしているような歪み 3.ゲインLで-2dBを超えると波形の下側が切れる歪み 原因不明.もしかしたら個体差かもしれない |
これらの歪みは,入力音量を少し控えめにするだけで
すべて回避できる.よかった(笑)
どれも聴感ではっきりとわからないような歪みで,普段の利用での
実害は少ない.しかし普通のデジタルレコーダと比べると
ちょっとした違和感に戸惑うことがある.次の文章で簡単にまとめた.
歪み 1 スウィープ信号でわかる高音域の歪み
Zoom H4は大きな音を入力すると高音域が歪んでしまう.
レベルメーターで-12dBが壁になっていて,ここを超えると少しずつ歪みが
あらわれる.スウィープ信号のサンプルを聴くとよくわかる.
| 正常 → レベルメーターで-12dBぴったりになるように録音したスウィープ信号 歪む → レベルメーターで-9dBぴったりになるように録音したスウィープ信号 |
可聴域上限の20kHzから400Hzに20秒かけて降りてくるサイン波なので
高い音からフェードインするように聴こえるはず.
-12dBでは正しく録音できている.
しかし,わずか3dB上げた-9dBではだめ.
-9dBでは高い音が変質してキュルキュルというノイズになっちゃう.
| スウィープ信号で判別できるこの歪みは,H4に採用されているZoom社独自の エンファシス/デエンファシス技術によるものとのこと. |
この現象は,ゲインL/M/Hのすべてのゲインモードで同じように起こる.
スウィープ信号 -12.0dB (20kHz-400Hz; Sine; Stereo)
| ゲインL | ゲインM | ゲインH (mp3) |
スウィープ信号 -9.0dB (20kHz-400Hz; Sine; Stereo)
| ゲインL | ゲインM | ゲインH (mp3) |
このように,ゲインモードを問わず,-12dBがひとつの目安になるようだ.
| デジタル録音機では一般に-0dB付近まで録音レベルを追い込むのが常道だが, H4では,あまりメーターの振りが-12dBを超えないように やや控えめに録音したほうがいい結果が得られるのではないかと思う. |
テスト信号を入れると凄い感じなので,これでまともに録音できるのかと不安になってしまう.
しかし,実際の楽器音ではほとんど耳で判別できない.-0dBまで突っ込んでも,
ちょっと音が暖かくなったかな,という印象.かえって音の厚みが増して
好ましいときもある.なんだか手品を見たような不思議な感じ.
しかし,ステレオの分離感を狙った録音や,繊細なマイクの持ち味を出す場合には
音が甘くなると不都合な場面も出てくる.そのときはレベルを控えめにしたほうがいい.
最後に,テスト結果そのままのWAVファイルを掲載しておく.
24bit/96kHz時の動作を確認するため,40kHzまでのテストも行った.
-12dBではこのテストを見事パスしている.
| → WAV: レコーダ動作時のスウィープ信号の録音 (20kHz - 400Hz, 16bit/44.1kHz) → WAV: レコーダ動作時のスウィープ信号の録音 (40kHz - 400Hz, 24bit/96kHz) |
歪み 2 RMAAテストでわかるゲインLの歪み
入力レベルによって歪みが起きることがわかったので,RMAAテストで
8段階にレベルを変えて計測し,数値の変化を見てみることにした.
すると,意外な結果に.
| RMAA: 入力レベルによる全高調波歪率(THD)/混変調歪率(IMD)の変化 ゲインL | ゲインM | ゲインH (-03.0dB 〜 -12.0dB) ゲインL | ゲインM | ゲインH (-15.0dB 〜 -30.0dB) |
主にTHD値を見てほしい.(IMD値はS/Nの変化の影響で比較が難しいので)
ゲインLのTHDで-3dBが0.518,-6dBが0.216という大きな値を示す一方,
他のすべての計測結果が0.1前後で収まっている.つまり
| -12dBを超える音量でのスウィープ信号で判別できる高域の変質は RMAAのTHD/IMDの値にほとんど反映されない |
当初,すべてのゲインモードで起きる高音域の変質を
数値で確認できると思ってたのに,なんてこった(笑)
しかもゲインLだけ数値が高いということは,ゲインLだけ
特別な歪みが加わっているということだから
| ゲインLでは-12dBを超えると,高域の変質に加えて 軽いオーバードライブのような歪みが加わる |
試聴用のサンプルファイルは用意できなかった.
(この歪みだけを取り出して聴けるようにするのは難しいため)
歪み 3 ゲインLの波形の下側が切れる歪み
かなりマイナーな問題なので,章立てて図入りで指摘すると大げさに
感じるかも.ゲインLの-2dB以上であらわれる歪みについて指摘する.
Sine 1kHz, -0.5dBFS, Unbal.Gain-L
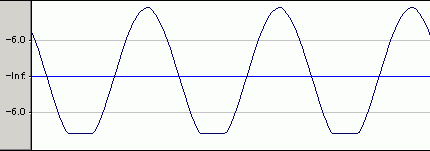
Sine 1kHz, -0.5dBFS, Unbal.Gain-H
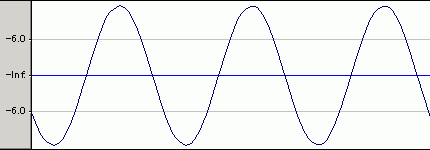
上がゲインL,下がゲインHでの録音.
デジタルクリップ直前の-0.5dBのサイン波を入れたところ.
ゲインLの波形の下が切れている.ゲインHは正常.
これはデジタルクリップやDC成分によって起きているのではない.原因不明.
約-2dBFSの位置で下側だけスパっと切れていて,さらに大きな音量を入れて
わざとデジタルクリップさせても,ここだけ-2dBになってしまう.
ゲインLのときだけ発生.入力1/2の両方で同じように起きる.
ゲインMやHではこの症状は起きないことを確認.ちょっと安心.
これはさすがに製品の個体による不良かもしれない.
音的な実害は少ないけれども,これ作った奴は恥ずかしいぞ(笑)
| こいつの問題は,音ではなくメーターの挙動にあらわれる. ゲインLのときにどんな音量で突っ込んでも ピークメーターが最大まで振り切れないんだよね. 最後の1ドットが点灯しない(笑) 何か変なリミッタ回路でもあるのかと思って焦った. |
SDカードの書込動作にシンクロした小さなノイズ
- AC駆動時は問題にならない.意識するのは電池駆動のときのみ.
- ごく小さいノイズで,ライン入力のゲインLでは90dB以下.
しかし内蔵マイクのゲインHだと-40dBまで浮いてくる.このときは
静かな部屋だとレベルメーターで視認できるようになる.
- SDカードのアクセスと同期しているので,16bitから24bitにレートを
上げるとノイズの間隔が早くなる(大きさはかわらない).
逆にmp3にするとアクセスが減るので間隔が長くなる.
- メーターを大きく動かしているのは,5〜80Hzのノイズ.
10Hz未満の超低域が主成分で,この帯域は耳に聴こえない.
目立って聴こえるのは同時に中音域に付随する小さなノイズのようだ.
- 2枚のTranscend TS2GSD150のそれぞれが特徴の違うノイズになっている.
同じ型番でも違うものだなあと実感.
乾電池駆動,ライン入力,ゲインHで無音状態を録音したファイルを
PC側で48dB増幅して,ノイズを聴きやすく拡大したもの.
sd_noise_catalog.mp3
1.Transcend TS2GSD150 #01
2.Transcend TS2GSD150 #02
3.Transcend TS2GSDC
4.MediaFo 128MB
5.Toshiba SD-M02G6R2W
の順番で約10秒ずつ並べた.各ノイズの波形は次のようなもの.
(見やすくするために増幅/拡大しています)
Transcend TS2GSD150 1枚目
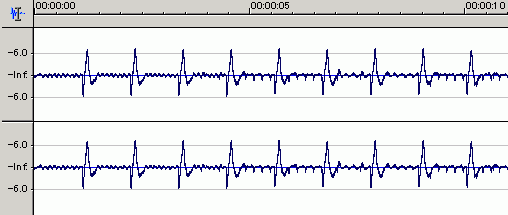
Transcend TS2GSD150 2枚目
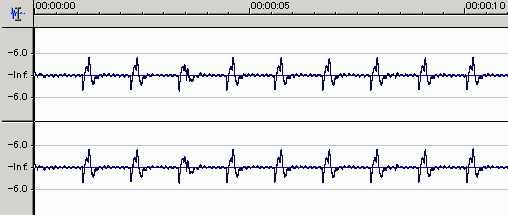
Transcend TS2GSDC
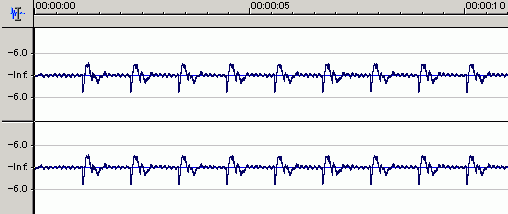
MediaFo 128MB
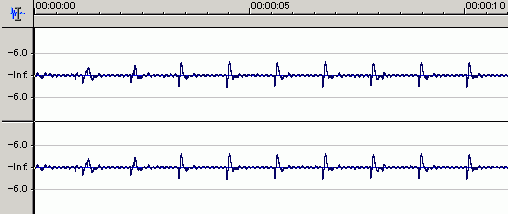
Toshiba SD-M02G6R2W
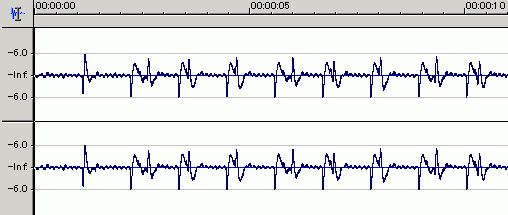
録音時そのままのWAVファイル.(mp3化や増幅などの加工をしていないもの)
Transcend_TS2GSD150_01.zip
Transcend_TS2GSD150_02.zip
Transcend_TS2GSDC.zip
MediaFo_128MB.zip
Toshiba_SD-M02G6R2W.zip
WAVファイル
→ WAV: レコーダ動作時のスウィープ信号の録音 (20kHz - 400Hz, 16bit/44.1kHz)
→ WAV: レコーダ動作時のスウィープ信号の録音 (40kHz - 400Hz, 24bit/96kHz)
USBオーディオ動作時のスウィープ信号の録音 (20kHz - 400Hz; v1.10)
USBオーディオ動作時のスウィープ信号の再生 (20kHz - 400Hz; v1.10)
USBオーディオ動作時のサイン波の録音 (1kHz, 4kHz, 10kHz; v1.10)
USBオーディオ動作時のサイン波の再生 (1kHz, 4kHz, 10kHz; v1.10)
USBオーディオ動作時のサイン波の録音 (1kHz, 4kHz, 10kHz; v1.0)
SDカード ノイズ計測時のWAVファイル Transcend TS2GSD150
SDカード ノイズ計測時のWAVファイル Transcend TS2GSD150
SDカード ノイズ計測時のWAVファイル Transcend TS2GSDC
SDカード ノイズ計測時のWAVファイル MediaFo 128MB
SDカード ノイズ計測時のWAVファイル Toshiba SD-M02G6R2WV
ファンタム給電時のノイズ (OFF,48V,24V)
* これらのWAVファイルの-06dB等の表記は,Zoom H4のレベルメータの値です.
RMAAテスト結果
計測結果のダウンロード (sav/html)
バッテリー駆動時の録音再生 16bit/44.1kHz 24bit/96kHz
バッテリー駆動時の録音 ゲインLow/Mid/Highを比較 16bit/44.1kHz
バッテリー駆動時の録音 ゲインLow/Mid/Highを比較 24bit/44.1kHz
バッテリー駆動時の録音 ゲインLow/Mid/Highを比較 24bit/96kHz
バッテリー駆動時の録音 48kHz時の16bitと24bit
→ RMAA: 入力レベルによる全高調波歪率(THD)/混変調歪率(IMD)の変化 ゲインL (1)
→ RMAA: 入力レベルによる全高調波歪率(THD)/混変調歪率(IMD)の変化 ゲインL (2)
→ RMAA: 入力レベルによる全高調波歪率(THD)/混変調歪率(IMD)の変化 ゲインL (3)
→ RMAA: 入力レベルによる全高調波歪率(THD)/混変調歪率(IMD)の変化 ゲインL (4)
→ RMAA: 入力レベルによる全高調波歪率(THD)/混変調歪率(IMD)の変化 ゲインM (1)
→ RMAA: 入力レベルによる全高調波歪率(THD)/混変調歪率(IMD)の変化 ゲインM (2)
→ RMAA: 入力レベルによる全高調波歪率(THD)/混変調歪率(IMD)の変化 ゲインH (1)
→ RMAA: 入力レベルによる全高調波歪率(THD)/混変調歪率(IMD)の変化 ゲインH (2)
USBオーディオ動作時のRMAAテスト結果 (v1.10)
USBオーディオ動作時のRMAAテスト結果 (v1.0)
* 特に明記していない場合は次の状態でテストしました
入力: アンバランスライン; アナログゲイン: Low; デジタルゲイン: 100
* dB値はレベルメーターの読み値です.
メーターは最大サンプル値を示すピークメーターで,単位はdBFSです.
録音時のdB値はデジタルゲイン = 100のときのレベルメーターの読み値です.
デジタルゲイン100はH4のデフォルト値で,A/D値を加工しないユニティゲインです.
* テスト結果に記される略号は次のような意味です
| STD=単体レコーダとしての録音時 (Standalone) USB=USB動作時 (USB) AR=AC駆動での録音 (AC,Recording) AP=AC駆動での録音 (AC,Playback) BR=乾電池駆動での録音 (Battery,Recoding) BP=乾電池駆動での録音 (Battery,Playback) UL=アンバランスライン入力でアナログゲインLow (Unbalanced,Gain-Low) UM=アンバランスライン入力でアナログゲインMid (Unbalanced,Gain-Mid) UH=アンバランスライン入力でアナログゲインHigh (Unbalanced,Gain-High) |
* THD/IMD変化テストのタイトルの-3.0dB,-6.0dBという数値は,
THD/IMDテストのサイン波のレベル値を示しています.
Zoom H4のレベルメーターの値です.
| 徐々に音量を下げながらRMAAテストを繰り返したことを示しています. |
* USBオーディオ動作時にRMAAのループバックテストを試そうとしたが,
録音入力が常にモニター信号としてラインアウトに出力されるので,
自己ループバックによるRMAAテストはできなかった.
* テスト信号の送出/受け側に使ったTascam DM-24の特性は次のようなもの
→ RMAA: Tascam DM-24
手元にある24bit/96kHz対応機材のうち比較的まともなものはこれしかないので.